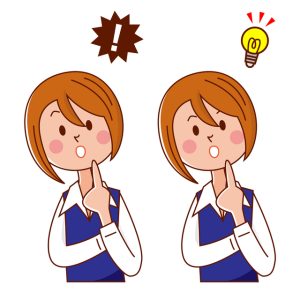すごく興味深い疑問ですね 🌱
実は、子どもの頃に覚えた言葉が記憶に残りやすいのには、脳の発達と感情の深さが関係しています。
🧠 子どもの脳は“吸収マシーン”
- 幼児期〜思春期の脳はシナプスの可塑性(柔軟性)が高く、新しい情報をどんどん吸収する時期。
- この時期に得た言葉は脳の深い記憶ネットワークに組み込まれ、長く定着しやすいんです。
🎈 感情と結びついた記憶は強い
- 子どもの頃に出会った言葉って、「初めて怒られたときのひと言」「親にほめられたセリフ」など、強い感情と結びついていることが多い。
- 感情のインパクトが強いほど、記憶にも強く焼きつくという仕組みです(これを“フラッシュバルブ記憶”とも言います)。
🔁 反復・日常の中での定着
- 子どもは日々、同じ言葉を何度も聞いたり使ったりするので無意識のうちに反復学習している状態に。
- 「あいうえお」や「おはよう」のような基礎語は、生活に密着しているぶん、忘れようにも忘れられないんですね。
🧩 “母語”の不思議
- 幼少期に習得した言語は、脳の**言語野(ブローカ野やウェルニッケ野)**が特に活発に関与する時期に学ばれるため、無意識的な反応として定着しやすくなります。
- たとえば、外国語で聞くよりも、母語で言われたほうが感情が動く…なんてこと、ありますよね。