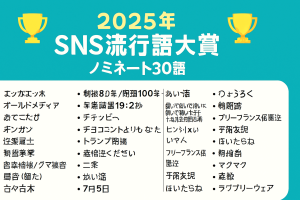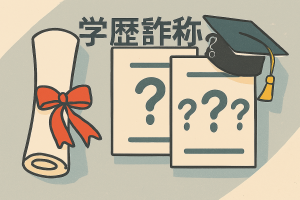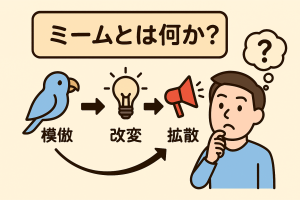概念の本質
「医食同源」は、食べ物と薬は本質的に同じ源から生まれ、どちらも健康を維持・増進する役割を担うという考え方です。
もともとは中国の「食薬同源」に由来し、日本では1972年に臨床医・新居裕久氏が「医」の字を当てて紹介しました。
この思想は単なる健康法に留まらず、日々の食事を通じて未病をケアするライフスタイルとして定着しています。
目次
東洋医学 × 現代栄養学
- 東洋医学
- 体質(寒熱・虚実)を見極め、食材の性質(温性・涼性)を使い分け
- 五行説や陰陽論で「体と自然の調和」を重視
- 現代栄養学
- 栄養素の定量的分析(ビタミン、ミネラル、食物繊維など)
- 食事バランスガイドや最新のエビデンスに基づく食習慣
両者を融合させることで「美味しさ」「手軽さ」「科学的根拠」が揃った実践法が生まれます。
実践ステップ
- 体質チェック
- 自分が「冷えやすい」「疲れやすい」「胃腸が弱い」など、持ちやすい症状をリストアップ
- 季節の食材を選ぶ
- 春→苦味でデトックス、夏→苦・寒性でクールダウン
- 秋→甘味で潤い補給、冬→辛温性で体を温める
- 調理法を工夫する
- 煮込み:体を温めたいときに最適
- 発酵:腸内環境を整える
- 感謝のマインドを添える
- 食材を調理する前に、その由来や季節を感じるひと呼吸を
季節ごとのおすすめ食材例
| 季節 | 食材 | 主な効能 |
|---|---|---|
| 春 | タラの芽 | 肝のデトックス促進 |
| 夏 | ゴーヤ | 体温上昇の抑制 |
| 秋 | サツマイモ | 乾燥対策・潤い補給 |
| 冬 | 生姜 | 血行促進・免疫力アップ |
日常への取り入れ方
- 朝食に発酵食品(ヨーグルト、味噌)をプラス
- 週1回は根菜をたっぷり使った煮込み料理を
- おやつ代わりにナッツや果物でビタミン補給
- 食後の散歩で消化を助け、心身をリセット
次にご提案したいこと
• 季節レシピの具体例(春の山菜リゾット、夏の冷製スープなど)
• 散歩×食材探索:近所で旬を感じるフィールドワークの方法
• 腸内環境を整える「発酵ライフ」入門
実践ステップの詳細
1. 体質チェック
まず自分の体質を知ることが、医食同源を効果的に取り入れる第一歩です。
下記の方法で「冷え」「疲れ」「消化」などの自覚症状を洗い出しましょう。
- 生活記録を3日間つける
- 起床時や就寝前の体温、睡眠の質、便通の状態をメモ
- 疲労感セルフスコアリング
- 朝・昼・夜それぞれ10点満点で疲労レベルを記録
- 舌・肌・お腹の観察
- 舌の色や苔の有無、皮膚の乾燥度、お腹の張りや痛みをチェック
2. 季節の食材を選ぶ
自分の体質データをもとに、旬の食材をマッチングさせます。
| 季節 | 体質例 | 推奨食材例 | 選び方のコツ |
|---|---|---|---|
| 春 | 体が重い、むくみ | タラの芽、菜の花 | 苦味で肝臓のデトックスを促進 |
| 夏 | ほてり、寝苦しい | ゴーヤ、トマト | 水分・ミネラルを補い、クールダウン |
| 秋 | 乾燥しやすい | サツマイモ、梨 | 甘味で潤い補給 |
| 冬 | 冷え、関節のこわばり | 生姜、根菜類(大根・人参) | 温性で血行促進、免疫力アップ |
選ぶ際は、産地や鮮度もポイント。できるだけ地元の直売所や農家から調達しましょう。
3. 調理法を工夫する
食材の効能を最大限に引き出すために、調理法も厳選します。
- 煮込み
- じっくり加熱して体を温める。根菜や生姜はスープやポトフに。
- 蒸し料理
- 水蒸気で優しく火を通し、旨味と栄養を逃さない。魚や鶏肉も◎。
- 発酵
- 味噌漬け、キムチ、漬物で腸内環境を整える。発酵時間は好みで調整。
- 生食・和え物
- 香草やナッツ、オイルで和えるだけ。栄養素を壊さず取り入れられる。
4. 感謝のマインドを添える
食材が手元に届くまでの過程に思いをはせることで、心身の調和が深まります。
- 料理前に「いただきます」の意味をかみしめる
- 食材の香りや色味をじっくり観察する時間を持つ
- 食事日記に「今日の旬」「感じたおいしさ」を一言記録