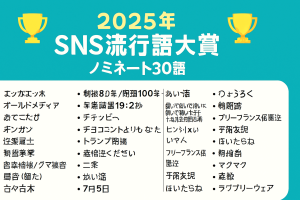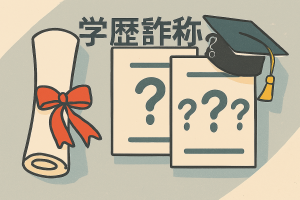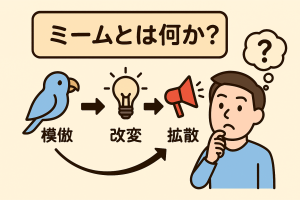「マイナスうるう秒」という言葉、ちょっと不思議に聞こえるかもしれませんが、実は非常に興味深い時間の調整方法です。以下で詳しく説明しますね。
目次
🕰️ うるう秒とは?
- 地球の自転はわずかに不規則で、原子時計による「国際原子時(TAI)」と、地球の自転に基づく「世界時(UT1)」との間にズレが生じます。
- このズレを調整するために、うるう秒が導入されます。通常は「1秒を追加」する形で行われます。
- 例:23時59分59秒の次に「23時59分60秒」が挿入され、その後に0時00分00秒になります。
⏳ マイナスうるう秒とは?
- これは1秒を削除するという逆の調整です。
- 地球の自転が予想以上に速くなり、世界時(UT1)が原子時(TAI)より進んでしまった場合に必要になります。
- つまり、**「23時59分58秒の次が0時00分00秒になる」**というような、1秒を飛ばす処理です。
🧠 なぜそんなことが起こるの?
- 地球の自転速度は、気候変動、氷河の融解、地殻変動などの影響で微妙に変化します。
- 最近の研究では、地球の自転が加速傾向にあることが観測されており、将来的にマイナスうるう秒が必要になる可能性があるとされています。
🌐 実際に導入されたことはある?
- まだ一度も導入されたことはありません。
- しかし、国際的な時間管理機関(たとえば国際地球回転・基準系事業 IERS)は、将来的な可能性として検討しています。
💻 技術的な影響は?
- うるう秒(特にマイナスうるう秒)は、コンピュータシステムやネットワークにとって非常に厄介です。
- 1秒が「消える」ことで、タイムスタンプの整合性が崩れたり、システム障害を引き起こす可能性があります。
- そのため、GoogleやMetaなどの企業は、うるう秒の廃止を提案しています。
地球の自転速度が変わる原因
地球の自転速度が変化する原因は、自然現象・地球内部の力学・気候変動などが複雑に絡み合っていることがわかっています。以下に詳しく解説します。
🌍 地球の自転速度が変わる主な原因
1. 🌕 月の引力(潮汐力)
- 月の重力が地球の海水を引っ張ることで「潮汐摩擦」が発生。
- この摩擦が地球の自転をわずかに遅くする働きを持つ。
- 長期的には、地球の自転は数千年単位で徐々に遅くなっている。
2. 🌬️ 大気・海流の変動
- ジェット気流や海流の動きが地球の回転に影響。
- 例えば、大気が遅く動くと、地球はバランスを取るために自転を速める傾向がある。
3. 🌋 地球内部の動き(核・マントル)
- 地球の内核やマントルの流動が自転速度に影響。
- 最近の研究では、内核の減速が外側の地殻の回転を速める可能性があるとされています。
4. ❄️ 氷河の融解・地下水の移動
- 氷が溶けて水が赤道付近に移動すると、地球の質量分布が変化。
- これにより、スケーター効果のように自転が速くなることがある。
5. 🌍 地震や地殻変動
- 巨大地震が地球の質量分布や回転軸に微妙な変化を与える。
- 例:2011年の東日本大震災では、地球の自転が約1.8マイクロ秒短縮されたという報告も。
📉 なぜ最近は「速くなっている」のか?
- 通常は潮汐力などで徐々に遅くなるはずですが、近年は加速傾向が観測されています。
- 2025年7月10日は「史上最も短い日」として、1日が1.38ミリ秒短かったと記録されています。
- この加速の原因はまだ完全には解明されておらず、科学者たちは地球内部の不規則な動きや気候変動との相互作用を調査中です。
🧠 まとめ:地球の自転は「生きている」
| 要因 | 自転への影響 |
|---|---|
| 月の引力 | 遅くなる |
| 大気・海流 | 速くなることも |
| 地球内部の動き | 加速・減速両方 |
| 氷の融解 | 加速する場合あり |
| 地震 | 微細な変化を与える |
地球の自転は、見た目には変わらなくても、ミリ秒単位で常に変動しています。
この変化が、うるう秒の調整や、将来的な「マイナスうるう秒」の導入につながる可能性もあるのです。